学生ベンチャーが救われた「会社の二重構造」
「会社」とはヒトなのだろうか、モノなのだろうか?シンプルなようでいて、突き詰めて考えていくとむずかしい問いかけだ。武田は学生ベンチャーとして起業して数年後にベンチャーキャピタルからの出資を受けると決めたとき、ある種の混乱に陥った。それは、「家族のようなドラマチックな唯一無二の関係」が、交換可能なお金で計算されるモノへと変わったことへの違和感だ。今回のゲストは、国際基督教大学客員教授の岩井克人氏。貨幣論の権威とベンチャー起業家というユニークな取り合わせでは、まずこの「違和感」の正体を考えてみよう。
「ロマンとそろばん」の同居
武田 エイベック研究所は学生ベンチャーから始まったので、最初はほんとに貧乏で、仲間同士、飽食の時代といわれる現代で空腹と戦っている自分たちを笑っていた時期もありました。それから、少しずつ組織も事業も大きくなり、自社開発に専念するため、出資を受けようということになりました。そうすると、ベンチャーキャピタルからは、投資の対象、つまり将来利益を生み出すかどうかという「お金目線」で見られるわけです。家族のようなドラマチックな唯一無二の関係が、交換可能なお金で計算される。それがなんとも違和感がありまして……。
岩井 その違和感は正しいと思いますよ。
武田 「僕たちの会社を他の会社と比べるな」とか(笑)。でも、ベンチャーキャピタルの方々と付き合ううちに、彼らもファンドの出資者に責任を持っていて、ファンドの出資者の方々も銘々の想いを乗せ、ベンチャーキャピタルにお金を託している。ベンチャーキャピタルだって、それらの約束を裏切らないために、私たちが出資するに足る相手かを見極めようとしている。だから当然、投資した後の利回りが他社と比べて優れているかどうかをしっかりと確認しなくてはならない。つまり、交換不可能なドラマと交換可能な貨幣。いうなれば、「ロマンとそろばん」ですね。この一見相反するふたつのことが、同時に起きていて、そしてどちらもリアルで誠実なことだとわかったんです。このあたりから、だんだん、混乱してきて……。
岩井 おもしろいですね、続けてください。
武田 理解できてからが大変でした(笑)。日々起こるさまざまな出来事が、あるときは交換不可能なドラマチックなものに見え、また、あるときはお金で換算できる交換可能なものに見える。どちらかが本当で、どちらかが間違っていると考えると、わけがわからなくなりました。
岩井 その感覚は非常に本質的だと思います。お金を貸すということは、英語で「クレジット」といいます。この語源は「クレド」といってラテン語で信仰、信条を表す言葉なんです。神を信じること、それが人を信じることにつながり、この人はお金を貸すに値する人だと信用してお金を貸す、という意味になったんです。本来、お金を貸すのは信用に基づく行為なんですよ。
武田 そうだったんですね。私は岩井先生の『二十一世紀の資本主義論』を読んで、「法人」という概念、つまり会社は「ヒト」であり「モノ」であり、その両義性を持つものだということが理解できて、混乱から抜け出すことができました。あのとき、クリアになった視界に助けられました。つまり、「法人」とはなにか?という問いに対する回答ですね。
岩井 理論が実践で役立っていると聞いて嬉しいです。人が集まって団体をつくる。その団体それ自体を法律上「ヒト」として扱うのが「法人」です。美術館などの「財団法人」で考えるとわかりやすいかもしれません。芸術や学術などの目的のために、誰かが寄付をしてまとまったお金があり、それで美術品を買う。その美術品の所有者はだれにしたらよいのか?でもそのお金を寄付したヒトは何人もいるかもしれないし、もう亡くなってしまっているかもしれない。そのとき、そのまとまったお金を法律上「ヒト」として扱うのが「財団法人」です。その法律上の「ヒト」が美術品を購入したり、契約したりすると見立ててしまうんです。「学校法人」は、教育活動それ自身を法律上の「ヒト」とする。すると、その学校法人は土地を所有したり、人を雇ったりすることができます。
武田 なるほど。そうすると、企業というのは……。
岩井 利益を追求するような組織や活動を「ヒト」として扱うのが「企業法人」ですね。そもそも、歴史的に会社というのは、イタリアの貿易商人たちが海外と遠隔地貿易をするために船団を組んだ「カンパーニャ」、そして中世ヨーロッパの「都市自治体」などが原型だと言われています。では、この都市自治体が、土地を所有している領主から免税や自治の権利を付与してもらうときに、その契約を誰が結べばいいと思いますか?
代表者を選ぶことで法人が契約を交わせる
武田 そうですね、その都市自治体の代表者でしょうか。市長とか?
岩井 ここが、「法人」が生まれるポイントなのですが、市長個人が結んだ場合、その市長が死んでしまったらまた契約を結ばなくてはいけない。都市自体は、何百年も続くかもしれませんからね。都市自治体に所属する全員がサインしたとしたら、そのなかの1人が亡くなったり、新しい人が入ったりしたら、契約の結び直しです。そこで、団体メンバーがN人いたら、団体自身をN+1人目のヒトとして扱い、領主と契約を結ぶという考えが生まれたわけです。
武田 でもそれだと、団体自身が実際に契約書にサインをすることはできないですよね?「ヒト」として扱うといっても、本当にヒトであるわけではないですから……。
岩井 そうなんです。そこで、その法律上の代表者を選ぶ。それが都市自治体であれば市長です。彼は先ほど出てきた単なる市長個人とは違って、「都市自治体」という法律上の「ヒト」の代表となる。この市長が市長としてサインすると、それは都市自治体がサインをしたことと見なすのです。そうすると、法律上の「ヒト」としての都市は、個々の市民の生命を超えた存在となり、いくら市長が交代しても維持されることになるわけです。これが会社になると、代表権を持った役員、代表取締役です。財団法人や宗教法人、学校法人なら、理事長ですね。
武田 預金口座をつくるなど、実務は「法人」にはできないですもんね。その人の行為が法人の行為だと見なされるような生身の人間が必要になる。その人が代表権を持っている。このしくみは非常に腑に落ちました。でも当時の私はその後、ふと不思議に思ったことがあったんです。
岩井 なんでしょうか。
武田 誰にも所有されることなく、モノを所有できるのがヒトだとすれば、法律上、企業法人はさまざまな資産をもっている立派な「ヒト」ですよね。でも、企業は株式というかたちで証券化されることにより、「モノ」として売買されています。これはどういうことなのだろうか、と。法人はヒトなのか、モノなのか……と悩んでしまったんです。
「モノ」を「ヒト」として扱う矛盾
岩井 それにはまず、資本主義の世界の見方を知ることが必要です。資本主義社会というのは、世の中をヒトとモノにはっきり二分します。ヒトというのは、モノを所有する主体。そしてヒト以外は、基本的にすべて所有される客体としてのモノにしてしまおうというのが、資本主義社会の基本原理です。テーブルやペットボトルなどの物体から、特許のような形のないものまで、それが価値を生み出すような存在であれば「モノ」です。アメリカでは奨学金だって、利益を生み出すモノとして売買されていました。
武田 株のようにでしょうか。
岩井 そうですね。1人ずつの奨学金では不安定なので、千人単位で奨学金をパッケージにして、証券化する。毎年平均すると、何万ドルかのお金が返ってくるものとして、その権利を売り買いするんです。
武田 すごいですね。
岩井 アメリカはなんでも証券化してしまいますからね。この原理で言うと、会社も利益を生み出すと予想される存在なので、モノとして扱う。それを明示的にしたのが株式です。法律上はヒトだけれども、モノの要素があるんです。
武田 不思議な性質ですね。しかし、株式を所有しているとはいえ、株主がその会社にあるパソコンを「株主であるおれのものだ!」といって持っていったら、それは窃盗になるんですよね。法人が所有しているモノは、株主のモノではない。
岩井 もちろんです(笑)。トヨタ自動車の株主が、トヨタ自動車の工場に乗り込んで「この車はおれのものだ!」といって持ち出したら、それは窃盗です。会社の株主は、会社資産の所有者ではないのです。
武田 株主は、株式を所有して売買することはできるけれど、会社の所有物については不可侵という二重の構造になっているわけですよね。これがなんとも、奇妙というか、精巧というか……。
岩井 本当に、誰がこんなこと考えたんでしょうね。株式会社は、人類が考えた最大の発明の一つだと思います。近代的な株式会社に近いものが生まれたのは、いろいろな説がありますが、1600年頃に始まった東インド会社からだといわれています。そこからイギリスで産業革命が始まったときに、この便利な株式会社のしくみをもっと整理しようという動きがあって、19世紀には今とほとんど同じような制度ができあがりました。でも、最初は株式会社って嫌われていたんですよ。
武田 えっ、どうしてでしょうか。
岩井 武田さんが感じていた疑問と同じです。ヒトじゃないモノをヒトとして扱うっていうのは、気持ちが悪いことなんです。近代精神に反するといわれたんですね。
武田 ここでいう近代精神とは何を指すのでしょうか?
岩井 近代以前の封建的社会というのは、身分がはっきりしていて、極端に言うと、日本の場合、武士以外は人として扱われていませんでした。女性、子どもなんかなおさらです。でも、福沢諭吉が「天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ人ノ下ニ人ヲ造ラズト云ヘリ」といったように、明治維新ですべての人間は平等になった。そして、それらのヒトとモノをはっきり分けたのが近代社会だったんです。
武田 それなのに、法人はヒトでもあり、モノでもあるという二面性を持った存在だったと。
岩井 そうなんです。近代の市民社会の出発点であり、いちばん基本的な原則である「ヒトとモノとを分ける」という考えに反して、資本主義の発達のために便宜上モノをヒトにしていたので、市民社会を擁護しようとする人にとっては「けしからん」存在だったわけですね。でも、一度導入してしまうと、こんな便利なものはない、と(笑)。
武田 それで、矛盾をはらみながらも世界中に広まったんですね。本当に法人というのは不可思議な存在です。なんだか、混乱から抜け出した当時の風景を思い出してきました。

「ヒト」でもあり、「モノ」でもある法人。株式会社は人類が考えた最大の発明のひとつである。
経営者がよく働くとは限らない、ストックオプション制度
武田 前回は、ヒトでもあり、モノでもあるという「法人」の、その精巧で不思議な両義性をテーマにしました。
岩井 では、その応用問題として、今回は「経営者」とはなにか?について深掘り深堀してみるというのはどうでしょう?
武田 よろしくお願いします。
岩井 アメリカ型の会社理論では、株主が会社のオーナーであり、その株主と契約を結び、その代理人として行動する存在が経営者です。
武田 それが、“企業とは「契約の束」である”という、ロナルド・H・コース(アメリカの経済学者。1991年にノーベル経済学賞を受賞した)流の考え方につながるわけですね。
岩井 はい。契約というのは本来、互いの利益のために、自由に結ぶことができるものです。結果が良ければ利益になり、悪ければ自己責任。それでは、オーナーである株主が、株価を上げるために経営者を一生懸命働かせるにはどうすればいいか。その方法のひとつが、ストックオプション(将来の決められた日時にあらかじめ決められた金額で会社から株式を購入する権利)だったんです。
武田 経営者も株主にしてしまえば、株価を最大化するだろうと考えたんですね。
岩井 はい、そうです。そういうインセンティブを与えて、経営者が自己利益を追求すると、株主の利益にもなる状況をつくろうとしたんです。それで1960年以降、アメリカではストックオプションで報酬を支払う会社が急速に増えました。でもこれは、根本的に間違っています。
武田 日本でも、1997年に導入されてからストックオプションが広まりました。
岩井 2001年のエンロン事件では、不正が発覚する前に経営者は自社株オプションを売り逃げて巨額の利益を得ました。そして、粉飾された利益情報を信じていた多くの株主は、大損をしたわけです。特にかわいそうだったのは、年金を会社の株で運用していた従業員でした。職だけでなく、年金も失ってしまった。経営者を株主の代理人とみなし、自己利益を追求させるというインセンティブを与えることで、倫理性への配慮から解放してしまったこと。ここが間違っているポイントだと私は考えています。
武田 経営者を株主にして株価を最大化させる、という方法が必ずしも株主の利益になるわけではないということが確認されてしまったわけですね。
岩井 はい。そもそも経営者は、株主と代理契約を結んだ代理人ではありません。会社と経営者の間の契約は、必然的に「自己契約」になってしまうからです。自己契約とは、元旦の断酒や節酒の誓いと同じで、なんの強制力もありません。それは、経営者が倫理観をなくしたら、なんでもできてしまう。経営者とは、実は、会社のために会社に代わって意思表示や行動をする、会社の「代表機関」であるのです。
武田 経営者が自分の“倫理ストッパー”を外してしまったら、「まったく働かなくても年間3億円の報酬をもらう」というように、自分に都合のよい自己契約ができてしまうというわけですね。
岩井 はい(笑)。たとえば、株式会社エイベック研究所(現クオン株式会社)とその代表の武田隆さん個人との契約は、代表者である武田さん自身がサインすることになります。自分に都合のいいことをいくらでも書き入れられる。つまり、「契約」そのものが成り立たない構造なんです。ここに株式会社の脆弱で魅力的な本質が表れます。経営者とは本来、観念的な存在でしかない法人を、ヒトのように現実社会の中で振る舞わせる存在なのです。たとえるならば人形浄瑠璃における人形遣いのような存在なんです。
経営者は人形遣い。自己を抑止して法人をヒトのように動かす
武田 人形が会社で、それをヒトのように見せるのが経営者、ということですね。
岩井 そうです。人形浄瑠璃は、法人の考え方とよく似た構造をしています。日本には昔からそういう伝統があったから、意外とすんなり「株式会社」という仕組みを受け入れられたのかもしれません。
武田 いまや世界中で大人気の「初音ミク」もまさにそうですね。空虚(エンプティ)なものに感情移入して、ひとりのヒトを見出すみたいなことが、日本人は伝統的に得意な民族なのかもしれません。
岩井 対して、西洋のあやつり人形は、人間が人形を糸で操っているところを見せるんです。
武田 人形浄瑠璃の場合は、操っている人ではなく、人形が主役になる、というわけですね。
岩井 そうです。人形浄瑠璃は、人形だからこそ、人間以上に人間らしく演じることができるという逆説を実現した芸術です。英語で人間を意味する「パーソン」のギリシャ語の語源は「ペルソナ」です。それは、演劇において登場人物の役割を表す「仮面」の意味です。古代ギリシャでも日本の能でも、演劇というのは仮面、または人形が行うものだった。もっと言えば、そもそも古代においては、共同体という一種の劇場の中で一定の役割を果たせる存在が一人前の人間であって、近代に入って、その役割を意味するペルソナが逆にその役割を演じる人間という意味に転化したのです。人間それ自体が、もともと法人であったといってもよいかもしれません。
武田 仮面をつけるとヒトは本音になれるというテーマで、劇作家の平田オリザ氏と深掘りしたことがあります。(平田オリザ対談)
岩井 それはおもしろい。ところで、世界の歴史の中で市場がサポートする商業演劇が成立したのは、ギリシャ・ローマ時代と近代ヨーロッパと日本の江戸時代くらいです。これらはどれも、貨幣経済によって巨大化した都市が長期間継続したところなんですね。
武田 商売として演劇が成り立つまでに、都市が育ったということですね。
岩井 そう。世界中の他の多くの文化は、宮廷文化だった。宮廷文化というのは、どうしても王様のご機嫌に沿うようになり、芸術としては十分発展しないことが多い。でも、人形浄瑠璃や歌舞伎は一般の町民がお金を払って観にいくものだったから、市場による批評に晒されたわけですね。
武田 つまらなかったら、客席から「金返せ!」というヤジが聞こえますね。
岩井 聞こえるでしょう(笑)。
武田 芸術といっても、芸術家ひとりが生活していくのは大変でしょうし、さらに組織をつくり動くのであればなおのこと、その運営には、みんなの生活を支える資金が必要になります。
岩井 そうです。その芸術にお金を払う人が、運営に十分な数に満たなければ継続できません。なので、互いに技を磨き合い、さまざまな芸術が華開く世界が生まれるには、ブルジョア、いや町民による都市が必要だったんです。江戸時代の日本は、ヨーロッパに比べて遅れた面はありましたが、商人資本主義が成立しており、芸術にクオリティを求め、活性した市場がそれを磨きに磨いた。この点が魅力です。
武田 『二十一世紀の資本主義論』によれば、都市は貨幣の流通を必要とします。貨幣が都市を生み、都市が市場をつくり、市場が芸術を育てたんですね。
岩井 まさにそのとおりです。日本のものづくりの技術が向上したのも、同じ理由からでしょう。ここで話を経営者に戻しましょう。経営者というのは、人形浄瑠璃の人形遣いみたいなものだと言いました。
武田 主役はあくまで人形、つまり会社ということですね。
岩井 人形浄瑠璃の人形遣いだって、自分の顔を観客に見せたり、恋人が観にきていたらちょっと目配せをしたり、自分の存在をアピールしたいかもしれませんよね。
武田 それをしてしまうとその舞台は……。
岩井 丸つぶれになってしまう(笑)。だから人形遣いは黒い布(黒衣)を被せられている。公と私を分けて考え、人形を人間のように、いや人間以上に人間に見せることに専心するという、公的な義務を負いなさいということなのです。人形遣いは自らの芸術的な技を、自分を輝かせるのではなく人形を見事に動かすことだけに活かす。そうして初めて、人形浄瑠璃の芝居が成立する。
武田 会社の代表機関である経営者も同じなのですね。
資本主義は人を信じて任せることで成り立っている
岩井 コーポレート・ガバナンス(会社統治機構)制度もそうですが、株式会社の中核に必要なのは、公的な義務を負うという経営者自身による自己制御の約束であって、自己利益の追求ではありません。
武田 その約束が「信任」なのですね。
岩井 はい。自己利益追求を原則とする「契約」では、自己利益の追求を制御することは不可能です。会社と経営者がむすぶ契約は必然的に自己契約になってしまうからです。
武田 地球を覆い尽くさんばかりに広がる資本主義。そのコア(中核)に株式会社という存在があり、さらにそのコアには、「信任」という、これまたなんとも人間的な……。資本主義は、最後は人間の美意識や倫理観に委ねられているんですね。会社をつくり育てるのは、なにも経営者だけではありません。すべての行動を雇用契約で約束することができない以上、大なり小なり、その責任の重さは違うにせよ、関係者全員が、株式会社と信任関係で結ばれているのだと思います。
岩井 信任という言葉をまったく忘れて、「契約」に置き換えてしまったことが、2007年のサブプライム危機の発端だと思います。
武田 起業して10数年ほど経ったころ、ふと、株式会社エイベック研究所と会話ができるような感覚が私の中に芽生えたんです(笑)。事業も組織も拡張の連続だったので、その中心に居合わせたというのも大きいかもしれません。創業メンバーである私がつくったにもかかわらず、会社が私とは別の人格を持ったひとつの存在になった感じがしたんです。子どもがいつのまにか大人になって、というような(笑)。会話ができるようになったこの感じが、僕にとっては信任関係に近いのかなと思います。裏切れないな、という気持ちというか……。
岩井 その感覚は、人形遣いが人形を大事にして、あがめるのと一緒かもしれません。人形を尊重し、自分はそのしもべであると考える。それが人形浄瑠璃という芸術の真髄であり、経営の本質なのでしょうね。人形浄瑠璃では、頭・首と右手を担当する「主遣い」、左手担当の「左遣い」、両足担当の「足遣い」の3人で1体の人形を操作します。その修業は、足遣い→左遣い→主遣いの順で始められ、主遣いを務めるには40年かかるといわれています。実は、この主遣いだけは舞台で顔を出している。これは観客側の「遣い手に対する興味の高まり」によるといわれていますが、主遣いとは「私」を抑え公的な義務に徹することができる存在であることの表現だと私は考えています。

人形遣いと経営者。両者に共通して求められるのは「私」を抑え「公」に徹する力である。
”お金で買えないモノ”が価値になる
武田 私たちが生きる資本主義の世界には、その最も中心に貨幣の存在があります。『二十一世紀の資本主義論』では、貨幣は、いつかどこかで何か別の商品と交換されるために保有される「交換の媒介」と説明されています。なぜ貨幣は、何かと交換できる役割を担えるのでしょうか?
岩井 その疑問に関しては、2つの代表的な学説があります。ひとつは、貨幣そのものにモノとしての価値が存在しているとする「貨幣商品説」で、もうひとつは、共同体の決まりや政府の命令、国家の法律などでそれが貨幣だと定められているとする「貨幣法制説」です。でも、私はどちらも、間違っていると思っています。
武田 それは、どういった理由からなのですか?
岩井 貨幣の起源は、金や銀など皆が欲しがる貴重なモノであった可能性もあります。また、頭の良い王様があるとき、何かを貨幣にすると命令したことによって始まった可能性もあります。 事実、昔はさまざまなモノが貨幣として流通していましたし、またコインの場合は、紀元前7世紀ごろに現在ではトルコ領内のリディアという国家の王様が発明したと言われています。ただ、どちらの可能性もあるということは、どちらも半分しか真実ではないということです。
武田 どちらかが、貨幣の始まりということではないんですね。
岩井 そうです。貨幣の起源としてはどちらの可能性もありえます。そして、現在からはどちらが実際の貨幣の起源であるかは、決めることができません。そして、さらに言えば、貨幣論としては、どちらも間違えている。 たとえば金銀が貨幣として使われていたとします。もし金銀のモノとしての価値、たとえば耳飾りとしての価値が、貨幣としての価値よりも高ければ、どうなると思います?
武田 貨幣としては使いませんね。そのまま恋人にプレゼントするほうが見返りが大きいかもしれません(笑)。
岩井 はい(笑)。だれもがその金銀を手元に置いて、耳飾りにするはずです。貨幣としての価値のほうが低いから、他人に貨幣として引き渡すなどというもったいないことはしません。ということは、それはモノとして使われ、貨幣としては流通しないということなのです。 逆に言うと、金銀でもなんでも貨幣として使われたとたんに、その貨幣としての価値はモノとしての価値を必ず上回っている。だから、人はそれを自分でモノとして使わずに、他人に他のモノと引き換えに手渡し、その結果、人びとのあいだで流通することになる。 つまり、貨幣商品説は理論として矛盾しているのです。
岩井 また、貨幣法制説も間違えている。日本で最初に流通した鋳造貨幣は和同開珎と言われていますが、国が貨幣として使えと命令しても、みんな使わなかった。銅でつくってあって、真ん中に穴が開いていて、読めない漢字が書いてあるから、おまじないに使うものだと思われてしまった(笑)。後世に発掘された和同開珎は、だいたい神社仏閣の下に埋めてあったんですよ。
武田 たしかに、物々交換でことが足りていたら、貨幣という考え方は必要ないですからね。
岩井 それで、日本政府はがんばって、貨幣の流通を促進するために蓄銭叙位令というのを出します。一定量の銭を蓄えた人には、位を上げてあげる。
武田 「貨幣法制説」が優勢のようにみえますね。
岩井 でも、それでも流通しなかった。国家がいくら命令しても、他の人が貨幣として受け入れてくれなければ、貨幣は貨幣として流通してくれません。 そして、その後11世紀後半から、不思議な展開が起こります。東シナ海を中心に中国、朝鮮半島との貿易がさかんになってきて、資本主義が発展してくる。そうすると交換の手段が必要になる。そこで、中国のお金を日本に輸入して使ったのです。まずは唐のお金ですね。でも唐が滅びて、宋になり、宋が滅びて明へ王朝が移り変わっても、唐銭、宋銭、明銭と、一緒に日本では流通していました。
武田 なくなった王朝のお金を使っていた、というわけですね。
岩井 そうなんです。もう、宋の時代に唐は何の権威もない。宋の人から見たら、自分が滅ぼした国のお金を使い続けているなんて、とんでもないことですよ。明の時代も同じです。すでに滅びてしまった中国政府が出したお金を、日本人が勝手に使っているわけですから、貨幣法制説は当てはまりませんよね。
武田 そうですね。日本政府の力は加わっていないわけですから。
岩井 途中からはもっとひどい状態になって、倭寇という日本の海賊が中国で悪質の偽金を作ったのですが、それも流通していました。こういう粗悪な銭貨は「鐚銭(びたせん)」といわれていました。「びた一文やらない」などというときの「びた」です。
武田 もう明らかに法の力は及んでいませんね(笑)。
予想で成り立っている「貨幣」のあやふやさ
武田 モノとしての価値もなく、政府も保証していないとなると……。
岩井 それが貨幣としてみんなが用いるとみんなが予想しているから、貨幣としての価値を持つということなんです。
武田 500円玉を「500円」という価値として受け入れてくれる人がいると予想できるから、500円の価値として商品と交換することができる。そして、将来においてもその人が、それが500円の価値を持つ貨幣として他の人々が受け入れてくれると予想していると予想できるから、ということですね。
岩井 さらに言うと、その将来の将来においても他の人々が、それが500円の価値を持つ貨幣として受け入れてくれると予想していると予想できるからです。そして……。
武田 予想がマトリョーシカみたいに延々と続いていきますね(笑)。無限に続く予想の連鎖が前提になっている、こんなあやふやな貨幣というものが、資本主義社会の中枢だなんて、なんだか危なっかしいですね。
岩井 基本的に金融のプロがしている投機活動も、同じことが起こっていると思います。債券や株式や外貨などから派生したデリバティブ(金融派生商品)なんかは、無限の予想がその価値を支えています。 ただ、同時に、デリバティブはものすごく不安定で、サブプライム危機を引き起こす要因になりましたけれど、その不安定さには限度があります。たとえば、変動金利のローンと固定金利のローンを交換する金利スワップというデリバティブがあります。それは、実際のお金のやりとりからはかなり離れていますが、固定金利が欲しい人と変動金利のほうがいいと思っている人とが存在していることは確かです。どこかで現実とつながっているんですね。
武田 実態から離れて予想が進んでいくことはない、ということですね。
岩井 そうです。これに対して、貨幣だけは、どこにも実需がないわけです。たんなる金属のかけらやきれいな紙切れでしかない。 その一番極端な形態が、電子マネーです。これはたんなる電子信号にすぎない。百円玉ならねじ回しとして使えるかもしれませんし、千円札なら鼻がかめるかもしれませんが、電子信号にはどこにもモノとしての需要はない。他人が貨幣として受けとってくれると予想するから自分も貨幣として受けとる。それだけなんです。その意味で、お金というものは、最も純粋な投機、実需なき投機に他なりません。本当に不思議な存在です。 でも、脱線しますが、これはお金だけの話ではなく、言語だってそうなんですよ。明日地球が滅びるというときに、外国語を覚えようとはしないでしょう?
武田 子どもに日本語を教えるのは、この先の未来も、日本語が日本の言語の基準として使われるだろうと予想しているからだ、ということですね。
岩井 そうです。言葉がないと人間社会が絶対に成り立たない。けれど、われわれ人間にとって最も本質的な役割を果たす言葉そのものが、貨幣と同じ予想の無限の連鎖で成り立っている。それは、資本主義だけでなく、人間の存在そのものが、あやふやで不安定なものに支えられていることを示しています。貨幣とは何かを考えることは、同時に人間は何かを考えることにもつながります。
ポスト産業資本主義時代における、お金の価値とモノの価値
武田 インターネット上で商品の交換と、貨幣(電子マネー)の流通が起こることによって、資本主義が純粋化していくと先生はおっしゃっています。インターネット社会は今後どのような発展をしていくのでしょうか。
岩井 インターネットというのは、人間の認識と非常にマッチしていると思います。最近の脳科学によると、人間が外界を認識するというのは、基本的にはシミュレーションにすぎない。 たとえば、われわれが見る世界はどこにも切れ目がありませんが、網膜の中の神経線維が束になっている中心部分は、実際には何も見えていません。しかし人間の脳は、その「盲点」の部分をつねに補正して、本当は何も見えていないのに、どこにも穴がないように、外の世界をシミュレートしている。われわれにとっての現実は、そもそも最初から仮想現実なのですよね。人間はそもそもバーチャルなリアリティの中に生きているんです。
武田 それでも、資本主義の純粋化には不安が残るという声もあります。インターネットが普及して、グローバル経済が発展すると、政府の介入や地理的な距離も関係なく商品が交換される。そして、電子マネーが普及すれば、人々が財布からお金を出す時間さえも必要なくなります。そうなると、貨幣の持つ投機性が際立って外在化してしまうという懸念です。
岩井 そうですね。たしかにインターネット経済市場は、システムの外部にある実体にまったく依存しない、抽象的なコミュニケーション空間といえるでしょう。そうしてたどりつく資本主義の純粋形態は、最高に効率的な市場になる反面、マクロ経済的には非常に不安定になる可能性があります。商売的にも、昨日の成功者が、明日の敗者になる危険性がある。 しかし、興味深い変化もあるんですよ。それは、お金の価値が下がり始めているということです。
武田 経済学者がお金の価値が下がるといえば、通常、モノの価値が上がるインフレーションの状況を指すのだと思いますが……。
岩井 通常であれば(笑)。しかし、ここでいうお金の価値とは、もっと本質的な価値です。ポスト産業資本主義時代は、産業資本主義と違って、どんどん工場を建てて大量生産すれば利益が出る時代ではありません。利潤は差異性からしか生まれませんから、収入を上げるか、費用を下げるかしなくてはいけない。収入を上げるには商品の差別化が必要です。もしくは新しい市場をつくるか。そして、費用を下げるには技術革新をしなければいけない。どれも、人間にしか生み出せないものです。
武田 以前は、原料を仕入れるのにも、工場を建てるのにも、お金があればよかったけれど……。
岩井 そう。お金で買えないものが、最大の資本になるんです。つまり、人間。人間はお金で買えない。人の頭脳や創造性が利益を出すんです。ポスト産業資本主義時代は、お金で買える工場ではなく、お金で買えない人間、とくに人間の創造性が最大の資本になるので、お金そのものの価値も弱くなっているんです。いま、お金の価値が大きく下がっているという新しい時代が来ているのです。
武田 人間という、お金で買えないものの価値が上がるということですね。まさにルネッサンスですね。以前、対談させていただいた社会学者の宮台真司先生がおっしゃっていた「モノが輝かなくなった」というお話(対談記事)や、情報社会学者の公文俊平先生がおっしゃっていた「人々のあり方が”知民“という姿に変わっていくラストモダン」のお話を想起しました。
岩井 一見すると、お金が活躍しているように見えますが、実は投資先がなかなか見つからないので、右往左往している。だから、その動きが目立つだけなのです。そして、短期的に利益を生み出す一番簡単な方法が泡沫的投機(バブル)ですから、バブルが起きやすく、そしてしょっちゅう崩壊する。
武田 短期的にリターンが大きい投資先にみんなが投資するから、どんどんバブルが起きやすい状態になるということですね。
インターネット経済市場でも、鍵となるのは誠実さ
岩井 私がおもしろいと思うのは、このポスト産業資本主義の中で、資本主義的にものすごく成功している会社は、お金儲けを最優先にせず、社会への貢献を前提としている非資本主義的な会社であるという逆説なのです。 それはまさにいまお金の価値が落ちていて、人はお金で買えないモノ、いやコトにしか価値を見出さなくなってきたことを示しているのです。グーグルやアップルなどはその代表例ですね。武田さんが経営されているエイベック研究所(現クオン株式会社)さんもそうだと思っていますが(笑)。
武田 はい。目指してまいります。 ビジネスを、利益をつくることと定義した場合、その利益をどのくらいの量、生み出せるのかというのが従来の指標でしたが、いまは、どのように生み出すかという質も問われている気がします。 売上を上げるためにはお客さまから期待してもらう必要がある。期待してもらうには信頼してもらわなければならない。信頼してもらうためには、期待に応えて信頼残高を上げ、その信頼残高を担保に次の期待を得る。まさに“予想の連鎖”という言葉をお借りすると、“期待の連鎖”が売上になるのだと思います。 それらはつまり、ネットワークの関係の中で起こる現象です。利益にも、クオンティティ(量)だけでなく、クオリティ(質)が求められています。ネットワークに対してどのように貢献し、どのような方法で利益を創るのか、まさに、クオリティ・オブ・ベネフィットが求められてくるのだと思います。
岩井 そう、つまり、ネットワークに誠実であるということが大切なんです。それは前回話した、経営者の公的義務という考え方につがっているはずで。リナックスやウィキペディアなども、インターネットという新しい市場で、信頼性や誠実さのある場を創っていますよね。
武田 最近、エンゲージメント(絆)が大切だという認識が、日本のマーケッターの間でもようやく広がってきました。今回の先生のお話をうかがって、「信頼」を連鎖していける組織や商品が、効率性とともに不安定性も同時に跳ね上がっていくインターネット資本経済の市場において、多くの味方を得るのだと確信いたしました。
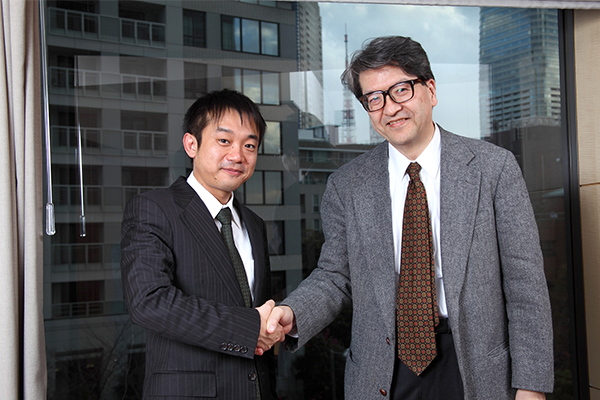
ポスト産業資本主義社会で成功しているのは、非資本主義的な会社。この逆説の中に大切なヒントが隠されている。

岩井克人(いわい・かつひと) 国際基督教大学客員教授。1947年、東京都生まれ。東京大学経済学部卒業。マサチューセッツ工科大学Ph.D.イェール大学助教授、東京大学経済学部教授などを経て、現在は東京大学名誉教授、東京財団名誉研究員、国際基督教大学特別招聘教授も務める。”DisequilibriumDynamics”にて日経経済図書文化賞特賞、『貨幣論』にてサントリー学芸賞、『会社はこれからどうなるのか』にて小林秀雄賞受賞、ほか著書多数。
