決して同じ気持ちになれなくても、つながることはできるんです。
オンライン上のコミュニティを活性化させるために「演劇」の力を活用すると聞けば、ちょっと意外だと感じるだろうか。だが、あながち突飛というわけでもない。
たとえば、インターネット上で率直に自分の意見を述べると、思わぬ反論が返ってきたり、不用意な発言をすれば“炎上”も招きかねない。しかしここに、あることを教える“先生役”と質問する“生徒役”といった役割を与えるとどうなるか。「自分が言ってるんじゃない、こういう役だからこう言ってるんだ」と役を盾にすることで、コミュニティ上のメンバーが一気に発言しやすくなるのだ。今回は劇作家・演出家の平田オリザ氏をお招きし、ソーシャルメディアと演劇におけるコミュニケーションの設計について考えていく。
劇作家はコミュニケーション・デザイナー
武田隆(以下、武田) 「ソーシャルメディア」と「演劇」というと、あまり接点がないように思われるかもしれませんが、じつは私たちのソーシャルメディア運営の手法の一部は、平田オリザさんが書かれた『演劇入門』を参考にさせていただいています。
平田オリザ(以下、平田) ありがとうございます。とても興味深いですね。
武田 オンライン上に活気あるコミュニティをつくるのはとても大変です。コミュニティに集まる人々に、「さあ、自由に話してください」といっても皆困ってしまう。その場の設定や役割の指定など細かい配慮が必要になります。これに演劇のメソッドが使えるのではないかと思ったのがきっかけでした。
平田 それはおもしろい観点ですね。僕は、演劇のなかで、他人と交わす新たな情報交換や交流である「対話」を発生させるために、完全なプライベートでも、パブリックでもない場として「セミパブリック」という概念を考えました。セミパブリックな空間というのは、たとえば、ホテルのロビー、大学のロッカールーム、職員室などです。プライベートな空間で話されることというのは、単なるおしゃべりや「ああ」とか「うん」といった相づちが多く、じつは対話は少ないものです。また、完全にパブリックな空間というのも、多くの人が通りすがりですから、やはり対話は生まれづらい。なので、対話を発生させるには、セミパブリックな空間が必要になります。
例えば、プライベートな場である家庭の居間であっても、設定によってはセミパブリックな空間になりえます。「娘の彼氏が初めて来る日」というように設定すると、「お父さんはずっと銀行勤めだから」と、登場人物がそれぞれの背景を説明してもおかしくなくなります。
武田 「他人」を登場させて、対話の構造をつくるということですね。
平田 はい。最近、教育の現場でも「対話型の授業」の必要性がいわれるようになってきました。演劇というのはずっとコミュニケーションをデザインしてきた分野なので、そのノウハウの一部を抽出すると、さまざまな分野のお役に立てることがあるわけです。
武田 だからこそ、私も演劇に惹かれたのかもしれません。ソーシャルメディアを運営するうえでは、対話が起こらないというのは致命的ですから。
平田 それを聞くと、しーんとした学校の教室を連想しますね(笑)。僕は、小中学校の表現教育についての学会に出席することがあるのですが、そのなかで「子どもたちが自分の意見を発表することを非常に嫌っている」という報告がありました。理由は単純で、目立つといじめの原因になるからです。いま学校外の社会もそうですよね。特にインターネット上で、不用意な発言をするとボコボコにされたりするじゃないですか(笑)。
武田 いわゆる「炎上」ですね。発言の場所と内容によっては、そういう事態もありえます。
平田 ところが、役割を与えると、とたんに子どもたちが発言しやすくなるんだそうです。「この役だから、こう言ってるんだ。おれが言ってるんじゃないよ」と、役を盾にできるからです。
武田 キャラクターを設定するんですね。
平田 そうなんです。それがうまく機能すると、話し合いのなかで深い本音がたくさん出てくるんだそうです。
「勝って目立つ」ことを極端に避ける、最近の小学生
武田 とてもよくわかります。私たちもソーシャルメディアでコミュニティをデザインするときには、まず役割(プラクティス)と報酬(インセンティブ)を設定します。たとえば、食品メーカーのコミュニティであれば、その食品を使った料理のレシピを作る人を先生ユーザー、その他の人を生徒ユーザーと設定する。このコミュニティのルールは、生徒ユーザーは先生ユーザーに質問し、先生ユーザーはもらった質問に対して回答することです。そして、質問した人、回答した人それぞれにプレゼントをわたす。役割と報酬が回り出すと、発言も増加します。
平田 まさに演劇ですね。インセンティブの必要性もわかります。これまでの日本の教育というのは、勝つことを目的とする競争原理をもとにしていました。しかし、いまの小中学生は、勝ち負けのあることでは積極的に動こうとしません。これはちょっと深刻な問題です。ここ10年ほど、小学生の体力測定の数値がちょっとずつ下がってきていた。その原因はモチベーションにありました。勝つどころか、勝とうと思っているのを見せるだけでもいじめられるので、みんなが勝つか負けるかぎりぎりのところを狙って、抑制して走る。
武田 自分の子供時代からは想像もつかない状況ですね……。
平田 そこで、最近の体育の授業では、勝ち負けではないモチベーションを引き出す教育の模索が始まっています。例えば、先ほどの先生ユーザーと生徒ユーザーのお話のように、跳び箱を飛べた子が、飛べない子に「なぜ飛べたのか」を言語で説明する試みが行われています。これは、国語教育と体育教育を結びつける好例でもあります。そうすれば、互いに尊敬もできるし、体育の力もついていく。インセンティブといっても、ニンジンをぶら下げて走らせるのではなくて、感謝や社会とつながっている感覚、そういったものが大切なんですね。
武田 そこにはインターネットも寄与できそうです。インターネットによってネットワークが可視化されると、感謝や評価も目に見えやすくなります。自分の活動が社会とつながっていく実感。これがソーシャルメディアで得られる最大のインセンティブといっても過言ではないと思います。
全部一緒じゃなくていい、一部分でも共有できればいい
平田 近代演劇というのは、主人公の気持ちに同化できるのがいい作品だとされてきました。いまでも基本的にはそういう作品がヒットしますよね。それに対し、1920年代にドイツの劇作家のベルトルト・ブレヒトという人が出てきて、出来事を客観的・批判的に見る演劇を提唱した。僕の演劇というのは、そのどちらでもなく、観客に空間を共有してもらうような感覚を持ってもらいたいと思っています。教育の現場でも、同じような問題意識を持っている方々がいます。シンパシー(同情)からエンパシー(共感)へ、つまり同一性から共有性へという考え方です。たとえば、いじめのロールプレイなどをすると、経験の浅い先生ほど「いじめられた子の気持ちになってごらん」と言うんです。
武田 つい言ってしまいそうな台詞ですね。
平田 でも、いじめられた子の気持ちに同化できるなら、そもそもいじめなんてしない。いじめる子には、いじめられた子の気持ちはわからないんです。でも、いじめる子も人から嫌なことをされた経験はあるはずです。そのときの気持ちと、共有できる部分を少しでもいいから見つけていく。それが重要な一歩になります。
武田 同じ気持ちになろうとするのではなく、それぞれの多様性を認めるようにしていくということですね。
平田 そのとおりです。共有できる部分だけを少しでも共有していこう、というのがエンパシー型の教育です。それは僕が演劇をつくっていくうえで、観客に求めていることでもあります。
武田 共感は、マーケティングの領域でも注目されはじめています。ソーシャルメディア上に表出される経験者の体験記に、高い効果があることもわかってきました。たとえば、英会話スクールの体験記では、まず経験者から、「英会話を習おうと思ったきっかけ」「スクールを卒業してから生活が変わったこと」「お勧めするとしたら、どんな人にどんな言葉で伝えるか」などの本音をオンラインのインタビュールームでじっくり聞き出します。そして、その体験談をまとめて公開する。すると、公開されたページを見た人の7.8%がその英会話スクールの無料体験レッスンに申し込むという結果が出ました。
平田 そうなるでしょう。
武田 これって、それぞれ生活やプロフィールがまったく違う人のエピソードに対して、共感が生まれているということですよね?
平田 まさに。そこがおもしろいところで、とことんパーソナルなもののほうが、共有できる部分が見つかりやすいんです。みんなに当てはまる大きな物語である必要はなく、個別のエピソードであるということがすごく大事です。僕の演劇も同じ構造です。共感のポイントを散りばめておいて、どこに共感してもらってもいいようにしてあります。2人で観に来ても、ぜんぜん違う芝居を観たような感想をもって帰ってほしい。意見がぶつかる可能性があるので、あんまりデートには向いてないですね(笑)。もうちょっと詳しく言うと、付き合ったばかりの恋人ではなく、この人と添い遂げる、という覚悟を決めた人と観てほしいです。
武田 平田オリザさんのお芝居を見ると、パートナーとの相性が確認できるというわけですね(笑)。
平田 そう(笑)。僕は公演のときによく、受付のところをウロウロしているんですけれど、老夫婦が感想を話し合っているのを見ると安心しますね。もうその段階になると、感想がバラバラでもいいじゃないですか。付き合いたてのうちは、やっぱり同じ感想をもって盛り上がりたいですよね。でも夫婦として長く連れ添うためには、違いも認め合わないといけない。つまり、武田さんもおっしゃっていることですが、やはり多様性が大切なんです。
今、ランダムをプログラミングする力が求められている
武田 平田さんの舞台を見ると、登場人物の行動がひとつひとつ腑に落ちるんです。たとえば、『東京ノート』に人生の一大決心をした次男が出てきますよね。何気ない一言に彼の心の深い葛藤が表れている。強烈なリアリティを感じます。平田オリザという劇作家はどこまで役になりきって台詞を書いているんだろうと驚愕します。
平田 じつはですね……、ぜんぜん深く考えてないんですよ。
武田 それはウソですよ(笑)。
平田 いやいや、本当なんです(笑)。武田さんみたいに、観客が勝手に共感して、編集してくれるんです。だから、脚本はギチギチに計算するのではなく、ランダムなほうがいいんですよ。
武田 すごいですね……。
平田 これからの社会で必要とされる能力は、ランダムをプログラミングできる力だと思っています。それは、ソーシャルメディアでも同じではないでしょうか。僕はいま、大阪大学の石黒浩教授の研究室と共同で、ロボット演劇をつくっているんですけれど、これまでのロボットというのは決められた動作を忠実に実行できるのがいいロボットだったんですね。
武田 産業用ロボットなどは、そうですね。
平田 でも、人間の動きというのはそういうものではない。たとえばコーヒーカップをつかむとしても、「手前でちょっと他の部分をワンタッチしてから取る」「全体の形を把握してから取る」など、いくつかの無駄な動きがあるんです。これをマイクロスリップと呼びます。僕は、認知心理学の学者と15年くらい共同研究を行ってきて、俳優の演技の巧拙は、このマイクロスリップに左右されるんじゃないかという結論に達しました。
武田 私たちの感じる「自然な動き」というのが、マイクロスリップによってつくり出されているんですね。
平田 そうです。ロボット研究の石黒先生も同じことを考えていて、彼は人間社会にロボットがとけこむ未来をつくろうとしています。そこで、どうしたら自然な動きができるロボットがつくれるかを模索していたんです。でも、認知心理学や人間工学の研究で数値を集めても、決まった平均値しか出てこなくて、マイクロスリップのような無駄がなくなってしまう。どれくらいランダムにすれば「自然な動き」になるのかが、わからなかったんですね。 そこで、ロボットの動きに対して「このセリフとセリフの間は0.2秒開けてください」「ここで首をちょっと傾けてください」など、細かな指示を出したんです。そうしたら、ものの30分くらいで、そこにいる全員がため息をつくくらい、人間らしい動きができるようになりました。僕たちのような芸術家は、どのようにランダムを組み込めばリアルな動きになるか、感覚でわかっているんです。
武田 演劇史2500年の蓄積ですね。
平田 なぜそうなるかは、わからないんですけどね。だから石黒先生は、僕が指示した間(ま)を解析してパラメータ化しているんです。この、ランダムをプログラミングしていく力が、あらゆるジャンルでこれから要求されていくんじゃないかと思うんです。
武田 マーケティングにも応用できるかもしれません。データで平均値を出しても、結局、誰も欲しがらないものになってしまいます。辛いものが好きな人と甘いものが好きな人の中間点は、辛くも甘くもないものになります。ライフスタイルが多様化していけばいくほど、平均値は意味をなさなくなりますね。

シンパシーからエンパシーへ。ソーシャルメディアも演劇も教育も“多様性”を認めることが重要な一歩になる。
話の上手な人は「冗長率」のコントロールが上手い人
平田オリザ(以下、平田) 人の話には「冗長率」というものが存在することをご存知ですか?
武田隆(以下、武田) 長くなる会話と短くなる会話があるということでしょうか。
平田 「冗長率」とは、あるセンテンスやパラグラフの中で、意味伝達と関係ない言葉が含まれている割合のことです。無意味な言葉が多ければ多いほど冗長率は高くなります。
武田 家族や恋人どうしの会話というのは、冗長率が高そうですね。
平田 それが、そうでもないんです。ごく親しい人々で交わされる「会話」は、意外にも冗長率が低いんです。内容は冗長なのですが、「あぁ」「まぁ」「いやー」などの無意味な言葉は滅多に含まれない。むしろ、長年連れ添った夫婦なんて「風呂」「めし」「新聞」など、まったく無駄のない会話をするでしょう?
武田 たしかに(笑)。
平田 そして、この冗長率は低ければ低いほうがいい、というわけでもないんです。もちろん演説やスピーチは低いほうがいいですよ。でも、他人とコミュニケーションするための「対話」は、相手のことを探りながら話す必要があるので、どうしても冗長率が高くなります。そして、話がうまい人というのは、冗長率を時と場合によって適切に操作できる人のことなんです。ニュース番組のキャスターも、気をつけて見てみると、夜7時のニュースと9時のニュースでは、冗長率を変えていることがわかります。
武田 私たちは基本的に、冗長率を低くするほうがいいと教えられてきたような気がします。
平田 従来の書き言葉中心の国語教育ではそうでした。でも、話し言葉はある程度冗長率が高く、先ほどお話ししたように(「同じ気持ちになれなくても、繋がることは出来るんです。」)ランダムなほうが伝わりやすいんです。きっと営業成績のいいセールスマンも、経験からこのことを知っていると思います。
これからは、その適切な冗長率をパラメータ化して、プログラミングしたり教育したりする方向に向かうでしょう。インターネットだと、やりとりのすべてがデータとして残るので、そのあたりも分析しやすいんじゃないでしょうか。
武田 たしかにそうですね。ソーシャルメディア上で育成されるオンライン・コミュニティは、発言やそれに対する返信などクリアに記録されるので、賑わっているのかそうでないのか、雰囲気だけでなく数値で把握することができます。
平田 なにかおもしろいことがわかりましたか?
イメージを共有する前に強いメッセージを押しつけられると、人は「引く」
武田 たとえば、あるコミュニティの活性の度合いを計る際、新しく投稿されたメッセージのうち、返信がついたメッセージの割合を見てみるんです。活性しているコミュニティの場合には、多くのメッセージに返信がついているのがわかります。返信率が高ければ高いほど、場は活性しているといえます。しかし、返信率が8割を超えるあたりからは注意が必要です。あまりに返信がついている状況は、コミュニティが蛸壺(一部の人のみが発言し、ほかの方が参加しづらい状況になること)化している危険性があります。 コミュニティを活性させるための手法として、私たちは「関与モデル」というものを採用しています。コミュニティで最初に口火を切って発言できる人は、参加者全体の中のごく少数です。でも、クリックするだけの「拍手」のような気楽で簡単なアクションになると、もっと多くの方が実行できます。そして、一度拍手を経験した人の発言率は向上します。 これらの現象が再現されることから、小さなことでも一度関与することで我が事化が生まれ、次のより大きな関与ができるようになるという仮説が生まれました。これが「関与モデル」です。
平田 それは、僕がよく言っている「セリフは遠いイメージから近いイメージへ」というのに似ているかもしれません。たとえば、戯曲をつくったことがない人に、「美術館にいる2人」という設定だけを渡して台詞を考えてもらうと「あー、やっぱり美術館はいいなあ」といきなり言ったりするんです。でもこれってわざとらしいし、ダサいでしょう(笑)。美術館には、静かであるとか、高尚な雰囲気があるとか、絵があるとか、監視員がいるとかいろいろな要素があるんですね。それを遠いイメージから並べ、「たまには静かなところもいいね」「もうちょっとゆっくり歩いてよ」「この絵、知ってる?この作者にはこんな逸話があって……」ときて、舞台からいなくなるあたりで「デートで美術館っていうのも、いいね」と言わせると、自然ですよね。
武田 ほんとですね。たしかに自然です。少しずつイメージの接点をつくって、近づいていくんですね。
平田 そうです。舞台で幕が上がって、いきなり出演者の2人が手をつないで「青春バンザイ!」っていったら、観客は引いてしまうでしょう。
武田 わけがわからないです(笑)。
平田 「引く」っていうのは、イメージが共有できていない段階で、強いメッセージやイデオロギーを押しつけられたときに感じるんです。昔は上意下達型の単純な社会で、若者は「引く」なんて言ったら社会に受け入れてもらえなかった。でも、それぞれが多様になった今はもうそんな上からの押しつけは通用しない。イメージをひとつひとつ共有していかなければいけません。 人の心は複雑で繊細です。だから、イメージしやすいものから、イメージしにくいものへ、ひとつひとつのイメージを確認しながら近づけていく。企業が伝えたいことにしたって、「これを買うといいですよ」というようなことは、ある意味イメージしにくいことですよね。
武田 いきなり「これ買ってください」って言われたら、それこそ「ドン引き」です。ソーシャルメディアに企業の広告が入ることに嫌悪感を感じる人が多いのも、心が引いてしまうからかもしれません。
平田 そうです。ソーシャルメディアは、人と人が、心と心でイメージを共有し合おうとしている場所でしょう?だから、「引く」という現象をちゃんと捉えて、段階を追ってコンテクストをすり合わせていかないと。
全てをわかり合えなくても、共有できる部分を見つける
武田 同感です。平田さんの演劇理論を知るうえで、この「Context(コンテクスト)」という言葉は必要不可欠な概念ですよね。通常、コンテクストは文脈と訳されることが多いですが、平田さんのおっしゃるコンテクストとはどういったものなのでしょうか?
平田 単純に言うと、その人がどういうつもりでその言葉を使っているか、ということです。地域や学校、家族など、どんな共同体も、コンテクストのすり合わせを無意識に行ってきているので、スムーズなコミュニケーションができるんです。一番わかりやすいのは夫婦ですね。夫婦というのは、異なるコンテクストで育った2人が暮らしはじめることなので、コンテクストのすれ違いが起こりやすい。電子レンジの呼び方だって、家庭によって「レンジ」だったり「チン」だったりするでしょう。そういう小さな言葉をすり合わせていくことから始まるんですよ。
武田 たしかに最初は些細な違いが気になるものですよね。
平田 ところが劇団員というのは、たかだか2ヵ月の稽古期間で、あたかも家族や恋人のように振る舞えます。もしくは、よく知っているのに他人のように振る舞うことを求められます。これは、表面的でもとりあえず共有できる部分を見つけて、コンテクストをすり合わせる訓練をしてきた成果です。演劇の本質がそこにあります。これからの日本人には、このコンテクストのすり合わせの技術が求められると思います。皆がそれぞれ異なるライフスタイルを持ちはじめたということもそうですし、また、加速度的に国際化も進んでいきます。だから、どんどん多様化する社会を生きるためには、コンテクストをすり合わせ、たとえわかりあえなくても、一定時間内にどこか共有できる部分を見つけていく。そうした力が必要になってくると思います。

これからは、恋人・夫婦も、演劇も、ソー シャルメディアも、マーケティングも「コ ンテクストのすり合わせ」技術が不可欠に なる。
「みんなちがって、たいへんだ」と認識する
武田隆(以下、武田) 今までは日本人の同質性が高かったからか、企業のマーケッターの中にも「消費者のことを知らないなんて恥ずべきことだ」と思っている方が多くいらっしゃいます。国際調査で海外の消費者を対象にすると「知らなくて当たり前」と思えても、自国日本の消費者が対象になると「知っているのが当然」となってしまいます。 ソーシャルメディアを観察していればわかりますが、これほど多様な生活者のリアリティを、全部知ることなどできるはずがありません。「私は知っている」というのは明らかな誤認です。
平田オリザ(以下、平田) まったく同感です。看護師や介護福祉士を目指す学生の中にも、「患者さんや障害者の気持ちがわからない」と悩んでしまう子がいます。真面目な子ほどその傾向がある。でも、患者さんだって、障害者だってみんな異なる個性を持っている。わからないのが当然なんです。僕は「当事者じゃないんだから、気持ちを全部わかることができないのは当然だ。でも君たちにも、患者さんや障害者の方の苦しみ、孤独、あるいは喜びで、共有できる部分があるんじゃないのか」と聞きます。
武田 たとえ一部であっても、共有できる部分は必ずあるということですね。
平田 そう。同一化できなくても、共有できればいいというと、楽になってくれる子は多いですね。
武田 多様なリアルがあることを認識してもらうわけですね。
平田 そうです。でも、これを学校現場で言うと、今度は、必ず学校の先生方は「あっ、金子みすゞの『みんなちがって、みんないい』ですね!」とおっしゃる。違うんですよ。「みんなちがって、たいへんだ」という話なんです(笑)。
武田 たいへんですよね(笑)。高度経済成長期は、消費者をひとくくりに捉えても、それで商品も売れていました。テレビも、冷蔵庫も、日本中のみんなが欲しがっていたのですから。「人並みになる」というのが合言葉でした。でも今は、そんな「消費者の全体」は存在しません。
平田 高度経済成長期の成功体験があまりに強かったので、企業の体質や仕組みが、いまだにそれをもとにしていますよね。この停滞した状況を打破する方法はみんなが欲しがるヒット商品を出すことだ、と思っている。その前提自体がもう間違っています。 昔は、冷蔵庫を買えば日本の家庭から食中毒がなくなったし、洗濯機を買えば主婦のあかぎれが一掃された。新しい家電を買うことで、目に見えて生活が豊かになりました。明らかな幸せがそこにはあったんです。でもいま、5センチ薄いテレビに買い換えたからといって、そんな幸せじゃないですよね。
武田 5センチも薄くするのは、大変な企業努力が必要です。しかし、それを求める消費者がいる一方、テレビは厚くてどっしりしているほうがいい、という消費者もいるのが現在の市場です。
平田 便利さやかっこよさって、人それぞれなんですよ。もう、ひとくくりにされた「消費者」をいっぺんに幸せにすることはできません。
上下関係、男女差別を生み出しやすい「日本語」
武田 企業内のコンテクストのすり合わせでいうと、私が経営するエイベック研究所にも独自の言葉の使い方があります。たとえば、戦略を立てる会議では、チームのメンバーを表記する際、それぞれの名前や役職を書かずに、アルファベットの略称で書く習慣があるんです。私は武田(TAKEDA)なので「TKD」と書かれます。
平田 おもしろい試みですね。
武田 これは何のためにやっているかというと、自分も含めたメンバーを純粋に利益創出のためのリソースとして捉え、フラットに戦略上に配置するためです。たとえば、コミュニティの企画を立てるフェーズでは、コミュニティの分析担当、モデレーター担当など、さまざまな知見を持ったメンバーが集まります。でもそこでメンバーが私のことを「社長」と呼ぶと、無意識に上下関係が生まれて、コラボレーションが起きにくくなってしまいます。「武田」という名前にしても、そこには私という人間のさまざまな要素が絡みます。でもアルファベットの略称を使うことで、これらの影響が緩和されます。「TKD」は、みんなの共有財としてのリソースであるという認識が強化されます。お互いの立場や事情、自分のことなのか他者のことなのか、こうしたことに過度に捉われることがなくなるんです。学生ベンチャー企業が生き残るために発見したノウハウのひとつです。
平田 あぁ、いいですね。いま、上場企業の4割が「さん付け運動」を導入しています。◯◯部長、などの役職ではなく◯◯さんと呼ぶようにするということですね。もともと日本語というのは、年長者・男性に有利な言葉なんです。武田さんが、部下にコピーをお願いするとしたらなんと言いますか?
武田 「コピーとっておいて」か「コピー、とっておいてください」でしょうか。
平田 それはごく普通ですよね。でも、女性の上司が男性の部下に「コピーとっておいて」と指示すると、少しきつい感じがしませんか?いまだに、女性の上司が男性の部下に命令するときの適切な言葉というのは、固まっていません。年上の男性患者さんが年下の女性看護師さんに「子ども扱いされた」とクレームを入れるケースもあるそうです。どれも日本語の問題です。これまでの日本語の歴史の中で女性が男性に指示する関係は、母親が子どもに指示する関係以外になかったからです。
武田 それぞれの関係性から、言葉は生まれていくのですね。
平田 そう。日本では、「会話」の言葉は発達してきたのですが、他者とディスカッションする「対話」の言葉はつくられてこなかったんです。だから、英語やフランス語に比べて、対等なほめ言葉も少ない。スポーツをするときは「ナイスショット!」など英語になるでしょう? 「いいぞ!」だと微妙に上から目線になってしまいますからね。
武田 「うまい!」「よかった!」っていうのも直訳みたいで変ですね(笑)。たしかに、フラットなほめ言葉というのは難しいです。
平田 でも、ひとつだけ、すごく汎用性のある言葉があります。それが「かわいい」です。これは何に対しても使えるんです。中高年の男性が「近ごろの若い女性は何でもかんでも『かわいいー!』ですませてしまう」と苦言を呈していることがありますが、女性はほめ言葉の非対称性を敏感に感じとって「かわいい」を多用しているんです。ボキャブラリーが乏しいのは、僕も含めた中高年の男性のほう。こういう汎用性のある言葉をもっと増やしていかないといけません。
武田 「対等な言葉」という点から考えると、「Respect(リスペクト)」という概念も理解が難しいようです。「尊敬」と訳してしまうと、下から上へ見上げるような眼差しになりますが、リスペクトのニュアンスはもう少し対等ですよね。私はあなたにとても影響を受けているという状況を伝えるならば、尊敬というより「尊重」と当てたほうがまだ近い。 インターネット、とりわけソーシャルメディアではフラットな関係が求められるので、このリスペクトの姿勢はとても重要なのですが、ぴったりの日本語がない。90年代の東京のクラブカルチャーなどでは、強引に日本語にすることをせず、リスペクトという言葉をそのまま使っていたように記憶しています。
平田 法律で男女雇用機会均等法ができても、日本語が変わらないかぎり、平等にはならない。言葉は社会の変化より、少しずつ遅れるんです。「さん付け」運動をいち早く取り入れた資生堂では、社長に就任したばかりだった福原義春さんが、自ら全社員に向けて「これからは、まず私を福原さんと呼んでください」と伝えたそうです。このようにまずは、言語的権力を持っている中高年男性が権力を放棄して、丁寧な言葉を使い、新しい対話の言葉をつくっていかないといけないと思います。
未来のため、必要な「対話の言葉」をつくっていく
平田 でも、この問題は必然とも言えるんですよね。日本は、英語やフランス語が150〜200年かけてやってきた言語の近代化を、明治期にたかだか30年くらいでやってしまったんです。コンテクストが時間をかけないとすり合わせられないように、言葉というものも放っておいたら自然にできるというものではありません。いま使われている演説、スピーチ、対論(ディベート)などの話し言葉は、明治の人たちが血のにじむような努力でつくりだしたものです。
武田 国の発展の過程で、やむをえず急ピッチでなされた近代化だったんですね。
平田 それでも、いいことではあるんですよ。言葉の近代化が追いつかなかった国では、高等教育がいまだに英語や旧宗主国の言葉で行われています。そういう国では民主化ができません。限られた階層の人しか政治や裁判に参加できないからです。同じ言葉で、政治の議論も井戸端会議もできないと、民主化は成り立たない。ただ、民主主義に一番大切な「対話」の言葉を欠くと、やはり危険な方向に国が傾く可能性もあります。
武田 ファシズムでしょうか?
平田 そうです。こうした対話の言葉がないと、排外的な独裁が起きやすいんです。日本と同じ時期に国家統一したイタリア、ドイツでもそれが起こってしまった。でも、ドイツはナチズムの大きな反省から、多文化共生社会を目指したんですね。 日本は移民も入ってこないし、その必要がなかったから、戦後も対話の言葉を生み出さないまま今まできてしまった。でも、ずっとそうとはかぎりません。これから何十年かで、グローバル化は必ず進む。その時代を生きるこれからの世代のために、いまの大人が知恵を出すべきだと思うんです。
武田 先ほどお話に上がった、対話を生み出す「他人」の存在が欠如しているのですね。 ドイツでは、若い世代でもそれぞれ支持政党を持っています。彼らは政党のことを「パーティー」と呼びます。エコロジーを標榜する「グリーン・パーティー」や、インターネットを使った双方向性を大事にする「パイレーツ・パーティー」など、それぞれのカラーもはっきりしている。政治に関する議論や、関与の仕方が成熟しています。ドイツ人に「日本と同じように、我々のところにも民主主義は外からやってきた」と言われると、いやいや全然レベルが違いますよ、と恐縮してしまいます。
平田 日本でも、もう一度民主主義とは何なのかを考える必要がありますね。
武田 今回の平田さんとの対談を通じて、個々人の感じている歴史観や未来に向けた希望をすり合わせることが大事なのではないかと思いました。そして、ソーシャルメディアはそういった場所をつくることが得意です。これからは、一部の知識層のみの言論ではなく、一般市民も参加できるコンセンサスの場をソーシャルメディアでつくれないかと思います。
平田 いいですね。そういった、双方向のワークショップ型の機関を、これからはマスメディアも持っていないといけないでしょう。そこにビジネスチャンスもあるし、社会変革の芽もある。そして、演劇のメソッドが活かせる部分もあると思います。
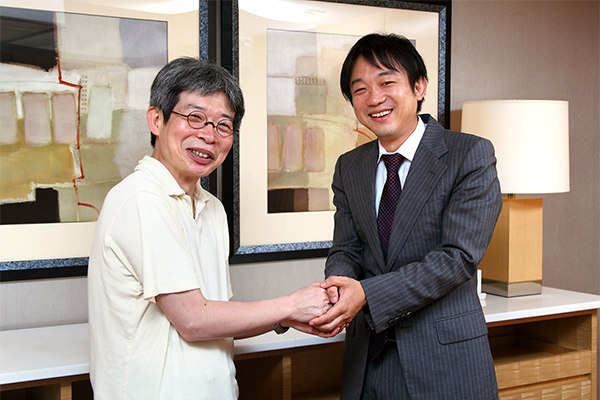
「対話」の言葉が発達していない日本。これからの世代のために、いま知恵を出し合うことが必要だ。

平田オリザ(ひらた・おりざ)劇作家・演出家、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授、四国学院大学客員教授・学長特別補佐、劇団「青年団」主宰、こまばアゴラ劇場芸術監督。1962年生まれ。1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞、2003年『その河をこえて、五月』で第2回朝日舞台芸術賞グランプリ受賞。フランスを中心に世界各国で作品が上演・出版されている。著書に『演劇入門』『わかりあえないことから』(以上講談社新書)、『幕が上がる』(講談社)等。ドキュメンタリー映画『演劇1,2』も公開中。
